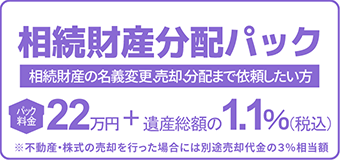配偶者への不動産の生前贈与
これまで

これまでは原則として、遺産分割において、生前贈与が贈与を受けた配偶者の特別受益(遺産の前渡し)として取り扱われるために、贈与を受けた配偶者の相続分が贈与不動産の価額分だけ減少することとなり、結果として、預貯金など以後の生活費の原資となるはずの金融資産を充分に取得できない恐れがあったため、生前贈与を利用しづらくさせる要因になっていたのではないでしょうか。
令和1年7月1日から
改正民法が施行され、婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の生前贈与をした場合に、その後、贈与した配偶者に相続が発生した際の遺産分割において、持戻し免除の意思表示があったものと推定する旨の規定が設けられました。
この推定規定が設けられたことで、原則として、生前贈与を特別受益として取り扱わずに配偶者の相続分を計算することになりました。
これにより、居住用不動産の生前贈与があった場合でも、遺産分割において、贈与を受けた配偶者の相続分が減少することがなくなり、預貯金など他の財産を取得できる割合が多くなりました。
税金面では
すでに相続税法上の特例制度(婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例)が設けられていますので、贈与税負担をゼロないしは大きく軽減することが可能です。
さらには、この特例を利用して贈与した対象不動産は、相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)とならず、相続税計算時の課税対象としてみなされないので相続税対策としてのメリットもあります。
今回の民法改正により、相続税法の特例と相まって、配偶者への不動産の生前贈与を安心して行えるようになったと言えるのではないでしょうか。